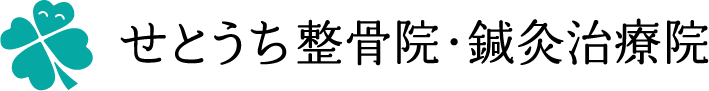こんにちは。せとうち整骨院の中村です。
出身は埼玉県で高校卒業後、大阪で8年ほど整骨院、リラクゼーションサロン、整形外科リハビリ室勤務、スポーツトレーナーを経験し香川県に来ました。以来県内の複数の系列整骨院で勤務し現在はせとうち整骨院で勤務しています。
たくさんの患者様と知り合えた事、症例に触れたことは今の私にはこの上ない経験となっています。これからも仕事を通じて皆様の健康のお手伝いができることをうれしく思っています。
占いはしていません
先日、鍼灸の施術中に患者さんから占い師みたいって言われました。
せとうち鍼灸整骨院では、占いは行っていません。(笑)
その患者さんは、強い肩こりと足の冷え、不眠症でお悩みの方でした。
鍼灸の施術をする前に、「脈診」と言って手首の脈を見ます。
「脈診」とは、東洋医学的な考えで施術をする場合、多くの方にすることです。
東洋医学では、体の不調を5つのタイプに分けて、何が足りていないか、何を補えばいいかを考えます。
患者様への説明の中で、性格や不調の原因をお話ししたところ、その方の周りに起こっていることとよく合っていたようでびっくりされたようです。
今回は、体質をタイプ別に分けた際の東洋医学的な考え方を大まかにご紹介します。
目次
1. 五行とは
五行とは、木・火・土・金・水という5つの要素で、自然や人の体もそのバランスで成り立っていると考えます。- 木(き):ストレスや筋肉のこわばりと関係
- 火(ひ):心臓や気持ちの高ぶりと関係
- 土(つち):胃腸の調子と関係
- 金(きん):肺や皮ふ、呼吸と関係
- 水(みず):腎臓や体のエネルギー、加齢と関係
2. 「木」の不調 ― ストレスや肩こり
- 症状の例:肩こり、頭痛、生理前のイライラや胸の張り
- 原因イメージ:気持ちやエネルギーの流れが滞る
- ケア方法:深呼吸やストレッチ、軽い運動で気分を発散。アロマや音楽もおすすめ。
3. 「火」の不調 ― 不眠や動悸
- 症状の例:寝つきが悪い、動悸、不安、口内炎
- 原因イメージ:体に「熱」がこもって心が休めない状態
- ケア方法:夜はスマホやテレビを控えてリラックス。カフェインを減らし、ゆったりした呼吸を意識。
4. 「土」の不調 ― 胃腸の弱り
- 症状の例:食欲不振、下痢や軟便、疲れやすい
- 原因イメージ:胃腸の力が落ちてエネルギーを作れない状態
- ケア方法:冷たい飲み物を控え、温かい食事を。腹八分目を心がけ、規則正しい食生活を大切に。
5. 「金」の不調 ― 咳や乾燥
- 症状の例:咳、鼻炎、皮ふの乾燥、風邪をひきやすい
- 原因イメージ:肺の力が弱くなり、外からの刺激に負けやすい状態
- ケア方法:加湿器で部屋を潤す。ウォーキングや深呼吸で肺を強くする。大根やはちみつもおすすめ。
6. 「水」の不調 ― 加齢や冷え
- 症状の例:腰やひざのだるさ、頻尿、不眠、耳鳴り、白髪が増える
- 原因イメージ:体の「元気のタンク(腎)」が減っている状態
- ケア方法:無理をせず休養をとる。温かい食事や入浴で体を温める。黒ごまや山芋、黒豆などを食事に取り入れる。
7. 季節ごとの養生のヒント
五行は季節とも深い関係があります。- 春は「木」:ストレッチや散歩で気を流す
- 夏は「火」:心を落ち着けて休養を意識
- 梅雨は「土」:胃腸にやさしい消化の良い食事
- 秋は「金」:呼吸法や乾燥対策
- 冬は「水」:体を温めてしっかり睡眠
8. まとめ
東洋医学的な考えを使うと、「今の不調はどの要素が乱れているのか?」を整理できます。治療には鍼灸や漢方が用いられますが、日常生活のちょっとした工夫でも改善を助けることができます。体と心のバランスを意識し、季節に合わせた生活を取り入れることが、東洋医学の知恵を活かした健康法といえるでしょう。
せとうち鍼灸整骨院では、こういった視点からも不調に対するケアを行っております。
今回ご紹介したのは、一般的なタイプ別でしたが、実際はいろいろな原因が重なり合っているケースがほとんどです。
症状を丁寧にお聞きして、患者様に合った施術を心がけております。
このブログの記事は「中村直樹」が書きました。